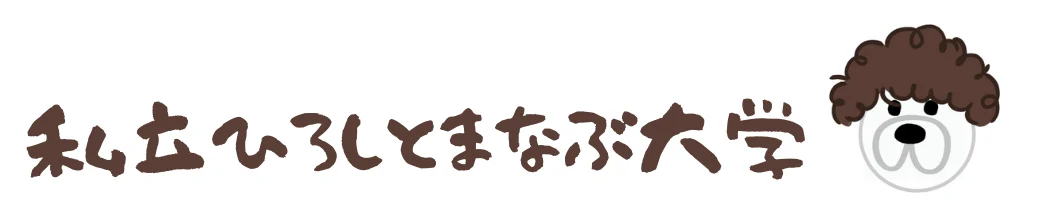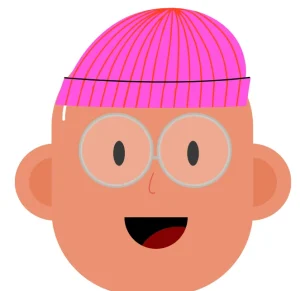
学長、2024年4月から私立大学も義務化されたという合理的配慮って何ですの?
いつどこに何を相談したら良いのか?相談したら何をしてもらえるのか?
分からないことが多すぎて自分が相談対象なのかも分かりません!
その質問、ひろしがお答えします。

近年学生さんからの相談が激増して全国の大学がてんてこまい状態の合理的配慮。
今回はこの仕組みで何が出来るのか?大学が抱えている問題点も含めて紹介します。
そもそも合理的配慮って何?
まずは「合理的配慮」という漢字5文字について大学の中でという文脈で説明します。
学生の皆さんには当然ながら学ぶ権利があります。
ところがですね、心身の病気や特性によって他の学生と同じように教室で授業を受けることが困難な学生さんもたくさんいるんですね。
通常の学びが困難な例
- 車椅子を使っているが教室に入るのに段差がある
- 難聴で先生の声が聞こえない
- パニック症状で人が大勢の中で授業が受けられない
- 起立性調節障害で朝早い授業に行けないことがある
- 発達障害でマルチタスクが困難、授業を聞きながらノートを取るのが苦手
- うつ症状や薬の副作用で学校に行けない時がある
- 感覚過敏で混雑した電車に乗るのが困難
これらはあくまで一例ですが、世の中のサービスは多数派の発想で作られています。

例えば私ひろしは左利きなのですが、スープバーのあのすくうやつが右利き仕様なもんだからすくいづらい時があります。
(語彙力が小学生レベル、、)
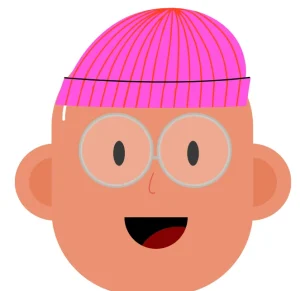
とにかくそんな風に『多数派に合わせられた環境、サービスでは学びが困難』となった時はお互いに相談しながら環境、提供するサービスの調整をしていこうね。
というのが合理的配慮です。
合理的配慮でどんな配慮をしてもらえるの?

リアルな世界において大学で働いていると、良くこの質問を受けます。
合理的配慮でどんな配慮をしてもらえるのかは、その子が何に困っているかによります。
- どんな困りごとがあるのかを聞いて、
- 希望する配慮内容を聞いて、
- その困りごとの根拠となるような資料も確認して、
- そういう状況であればこんな配慮が出来るかなと思うけどどうだろう?
こうしてお互いに対話を重ね、必要な配慮内容を決めていくことになります。
この際に、学生さんの希望する配慮内容について、
- 根拠が確認出来なかったり
- 合理性に欠けていたり
- 本質(授業内容や成績評価基準)を変える必要があったり
- 対応が大変すぎたり予算が足りなかったり(過重な負担)
そういう時は話し合い(対話)の中で調整していきます。
最近は特にオンラインで授業を受けたいという相談が多いですね。
オンライン受講が可能かどうかは各授業の実施形態にもよるのでケースバイケースです。
- オンライン受講で困りごとが解消されるのかどうか?
- オンライン実施が教員にとって過重な負担とならないか?
- オンラインでも同等の学習効果が得られるか?
- 他の学生に不利益が生じないか?
といったところを考慮しながら調整していくことになるかと思います。
合理的配慮では出来ないこと
合理的配慮の申請をしたからといってなんでもかんでも配慮してもらえるわけではありません。
大学によって判断、解釈の差はあるかもしれませんが以下のような配慮は提供することが難しいです。
合理的配慮の提供が難しい例
- 授業の本質(授業形態、到達目標、成績評価基準等)を変えることになる
- 他の学生に不利益が生じる
- 既に終わっているものに遡る
- 予算的にも労力的にも負担が重すぎる
グループワークや発表スキルを上げることが目的の授業において課題提出でOKにしてもらう。
これは授業の本質を変えることになるので不可。
グループワークが苦手な学生がいるのでこの授業ではグループワークはやらない。
これでは他の学生に不利益が生じるので不可。
一回も授業に出ていないがこれまでの欠席はなかったことにして欲しい。もしくは今から課題で代替して欲しい。
ケースバイケースな面はありますが、合理的配慮は過去に遡るものではないので不可。
全ての校舎にエレベーターを付けて欲しい。
校舎によっては建物が古く、場所によってはエレベーターで行けない教室もあるかも。
構造上エレベーターの設置が難しいこともあるでしょう。
そんな時には代替手段を考え、教室変更で対応することも。
建設的な対話の中でお互いの妥協点を見つけていくことも合理的配慮を提供していく上では大切なポイントでしょう。
合理的配慮の申請はどこでしたら良い?
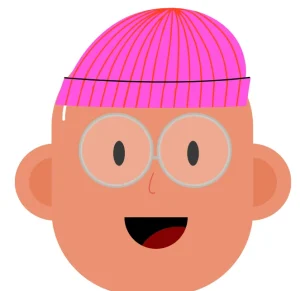
合理的配慮のことは何となく分かったけど、じゃあその相談をどこにしたら良いのでしょうか!?
授業の先生?専門の窓口?教務課の窓口?
どこに相談してもOK!が理想的ではありますが、、

合理的配慮はまだまだ大学内に浸透しているとは言い切れない制度です。
人によって対応に大きな差があり、先生に相談したけれど全然話を聞いてもらえなかったというケースも正直あります。
普段から密にコミュニケーションが取れている先生とでしたら直接話してみても良いですが、他の授業やその後の就職活動も考えると支援担当の窓口に相談してみるのをおすすめします。
大学によって窓口は異なるので、【自分が在籍している大学名+合理的配慮】でまずは検索してみてください。
教務課の窓口が申請先になっている大学もあれば、障害学生支援の専門の窓口が申請先になっている大学もあります。
合理的配慮は授業だけでなく、学生生活全般や就職活動にも関係してくる話です。

個人的な意見ですが、申請先が教務課の窓口の場合、対応する職員の経験値に左右される面が否定出来ないかな。
障害学生支援の専門部署があり、授業から学生生活から就職支援まで面倒を見てくれた方が安心だとは思います。
大学入学後に配慮が必要な学生や保護者の方は各大学の合理的配慮対応がどれくらい進んでいるかも確認しておいた方が良いです。
合理的配慮の申請に必要なものは?
合理的配慮の申請に必要なものは基本的には以下の2点。
- 申請書(大学によってフォーマットは様々でオンライン申請の場合もあり)
- 根拠資料(診断書、障害者手帳の写し、心理テストの結果等)
申請書には自分の状況や希望する配慮等を書ける範囲で記入してもらいます。
相談出来る部署がある大学の場合は、コーディネーターさんに相談しながら作成してみると良いでしょう。
まだまだ体制整備が追いついておらず、相談窓口を設けられない大学もあるのが実態ではありますが。
合理的配慮申請後の流れ
合理的配慮の申請書類が揃いましたらそちらと事前の相談や面談内容をもとに配慮文書を作成します。
支援部門で作成する大学もあれば、教務課や教員が作成するところもあるでしょう。
合理的配慮申請の流れ
- 事前相談
- 申請書提出
- 面談の中で対話し、配慮内容を調整
- 教員に送る配慮依頼文書を作成
- 学生との間で内容確認
- 確定した配慮文書を履修している授業の先生方に送付
大体の大学がこんな感じの流れで進んでいきます。
具体的な流れか自分が所属している大学のサイトにて調べてみてください。
手厚い大学でしたら配慮依頼後もフィードバックの面談をしたり、配慮依頼文書を送った教員にヒアリングやアンケート調査を行ったりもしています。
【要注意!!】合理的配慮は過去に遡るものではない
合理的配慮は基本的に相談を受けて配慮内容が決定して以降からスタートします。
良くあるのは全ての授業が終わってから診断書を持って窓口に学生が相談に来るケース。
この状態で相談しても、既に終わってしまったものに対して遡っての配慮を依頼することは困難です。
欠席していた分をチャラにして救済措置を講じることは出来ません。

合理的配慮は学ぶための環境を調整し、スタートラインを揃えるものであって、終わってしまった授業に対する救済措置ではないのでその点は注意してください!!
とは言えね、なかなか相談に行けない状況だったのだとは思います。
相談に来てくれただけでも大きな一歩ですから、次の学期に向けて必要な配慮を一緒に考えていきましょう。
終わってしまったからもう駄目だ、、
と思わずにそこからでも良いので相談窓口に困っていることを相談してみてください。
合理的配慮からその先の就職まで
合理的配慮の対応で悩ましい点の一つに就職への接続の問題があります。
配慮が必要な学生のことを把握できてもその先の就職に向けた支援に繋げることが出来ません。
- 配慮依頼で単位が何とかなれば
- とりあえず卒業を考える
- 今の状態では就職は無理だろう
- 就職は難しいので大学院進学を考えたい
といった理由から在学中に就職に向けたアクションまで繋げられず、その後どうしているのか分からないケースが殆ど。
所属している大学によって就職課の方の障害学生支援状況もまちまちだと思いますし、卒業してしまったら利用することが出来ません。
とりあえず卒業を優先したけどその後は未定という場合は、まずは就労移行支援事業所に相談して、一歩を踏み出してみてください。
まとめ:合理的配慮を利用して学びを継続しよう
今回のテーマは合理的配慮という制度について、申請の流れ、出来ること、出来ないこと、その後の就職に向けてでした。

なるべく分かりやすく説明しようと思ったので詳細は端折ったところもあります。
具体的な手続き方法は自分が所属する大学のウェブサイトで確認してね♪
世界のトップ大学の障害学生支援状況を調べてみると、支援を受けている学生が全体の10%以上だったりします。
一方で日本の大学はまだ1%ちょっとです。
更に足元では小中学校における配慮の件数は大幅に増えており、大学も合理的配慮による支援の拡充が急務な状況となっています。
が、残念ながら「予算がない。人が足りない。」といった理由で大学の支援体制はなかなか整っていかないのが現状ではあります。
配慮が必要な学生一人一人が抱え込まず、一歩踏み出して相談してみることで、日本の大学も成長していけると思います。
「こんなこと相談しても相手にされないんじゃないかな??」
そんな風に抱え込まず、まずは相談しやすいところから一歩踏み出してみてください。

皆様の一歩を全力で応援しております。